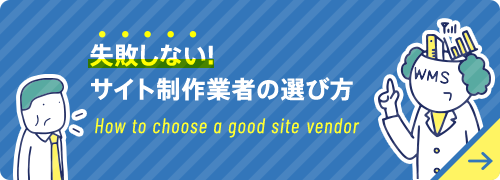かかりつけ医から考える「ワンストップ」
ワンストップという言葉は抽象的なイメージに聞こえるかもしれませんが、
じつは私たちの生活の身近なところにたくさん存在しています。
例えば、かかりつけ医。
体調がすぐれないときにまず相談に行く地域のクリニックは、まさにワンストップの好例です。
かかりつけ医は、患者のこれまでの病歴や生活習慣を踏まえて症状を総合的に判断し、
適切な検査を実施したり、多くの分野から必要な専門医を紹介したりしてくれます。
私たちは専門知識がなくても、適切な治療へと導かれるのです。
これこそがワンストップの力です。
では、もしかかりつけ医が存在しなかったらどうなるでしょうか。

胸の違和感に不安を覚えた人が、自分の判断だけで循環器内科に行き、
「専門が違う」と別の病院を勧められ、さらに別の診療科へ回される。
診断がつかずに症状が進行してしまうこともあるでしょう。
医療機関を転々とすれば、検査結果や病歴がバラバラに管理され、
医師ごとの方針が食い違って混乱を招くこともあります。
最悪の場合、医師同士が「自分の領分ではない」と言い合い、治療が進まない事態すら起こりえます。
薬についても同様です。
複数の医療機関にかかるうちに、成分が重複する薬が出されてしまい、
過剰投与による副作用を起こすリスクが高まります。
これは、患者自身では全体像を把握しきれないことが原因。
「ワンストップで全体を見てくれる存在」がないから起きる不都合です。
現代は医療に限らず、あらゆる分野で専門が細分化、高度化しています。
だからこそ、専門家同士をつなぎ、
全体を俯瞰して最適な道筋を示してくれる灯台のような存在が重要。
それがかかりつけ医に代表されるワンストップの機能です。
それは単なる便利さではなく、迷走やムダから私たちを守る安心の仕組みでもあるのです。